ニュースレターNo.89/2025年3月発行
インターネットことはじめ イーサネット
LANの代名詞
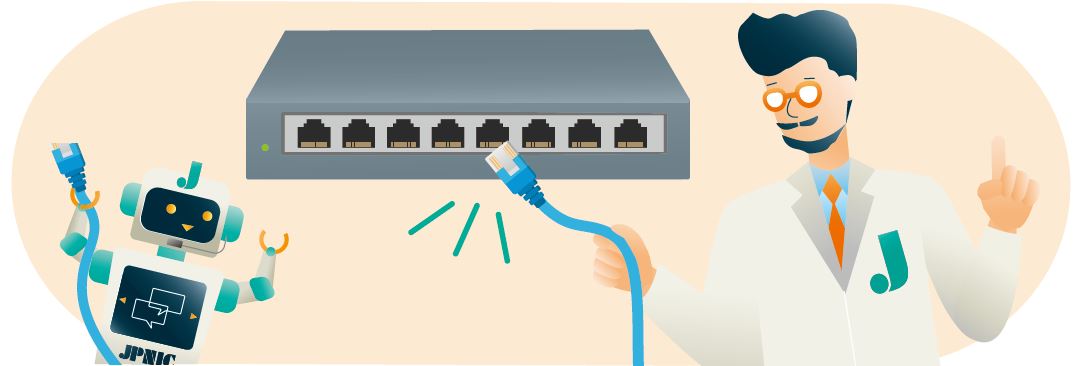
イーサネットと言えば、現代ではLAN、ひいてはネットワークの代名詞です。 さすがにモバイルの世界は無線なので、 有線であるイーサネットはマイナーですが。 一口にイーサネットと言っても、実はさまざまな規格があります。 新しい規格に準拠した製品は古い規格をサポートすることが一般的なので、 ユーザーが気にする必要はほとんどないのですが、 まれに古い規格でつながってしまって速度が出ない、 といったこともあります。
最初のイーサネット
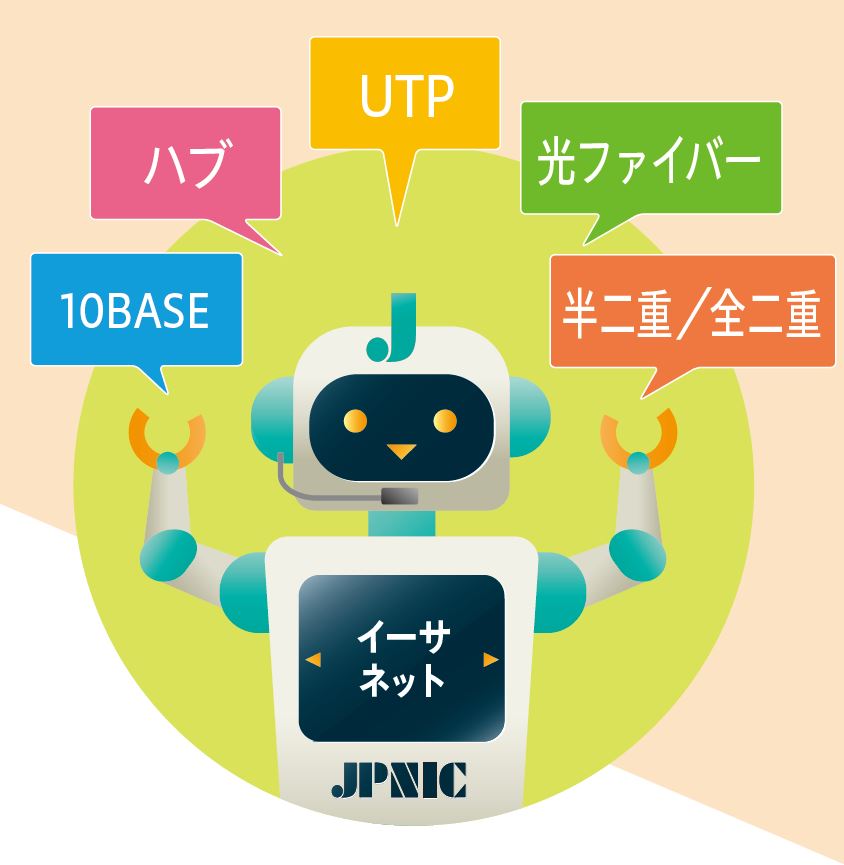
イーサネットの原点になったネットワークとして、 1970年にハワイ大学で開発された「ALOHA」が挙げられます。 ALOHAは無線によるネットワークでしたが、伝送に共有媒体を使い、 別の伝送と衝突した場合は後で再送を試みるというコンセプトが、 後のイーサネットの発想につながりました。
その後、1972年に米国のXEROX社・Palo Alto研究所で開発された、 世界初のGUIを備えたシングルユーザー用パーソナルコンピュータとも言われる、 AltoのネットワークにALOHAのアイディアが取り込まれ「Alto Aloha Network」として開発されました。 これが、現在のイーサネットの直接の祖先となっています。
1973年にこのネットワークが、イーサネットと名付けられました。 1979年にはイーサネットのデータ形式として、DEC (Digital Equipment Corporation)社/Intel社/XEROX社の3社が開発し、 3社の頭文字を冠した「DIX仕様」が公開され、 1980年にIEEE 802標準化委員会にイーサネット1.0として提出、公開されています。 1982年にはその更新版であるイーサネット2.0が策定され、 これをベースにIEEE 802.3 Standards for Local Area Networks※1として1983年に標準化後、 1997年のIEEE 802.3xの改版を経て、現在に至っています。
配線の変化
最初に標準化されたイーサネットは10BASE5と呼ばれ、 直径1cmほどの同軸ケーブルが用いられました。 一般的な感覚だと、かなり太い、TVのアンテナ線といった感じです。 ただこのケーブルがPCのコネクタに直接つながるわけではなく、 間に変換用の機材が必要になるなど、かなり仰々しい接続方法でした。
もう少し手軽な方法として、1985年に標準化された10BASE2が普及しました。 同じ同軸ケーブルでも、直径5mmほどの細いサイズのものを使います。 PCやワークステーションにはT字型のコネクタがあり、 このコネクタ間を細い同軸ケーブルで数珠つなぎにしていく方法です。 配線を変更するときに通信が途切れてしまったり、 通信できる距離が短くなったりといった問題もありましたが、 簡便さというメリットの方が大きかったようです。
現代では当然となっている、 ハブとUTP (Unshielded Twisted Pair)ケーブルを使った接続方法は、 1990年に標準化された10BASE-Tによって普及しました。 10BASE2と異なりホストを増減しても通信が途切れず、 ケーブルもさらに扱いやすくなっています。
イーサネットには電線ではなく、 光ファイバーケーブルを使った規格もあります。 外来雑音に強い、長距離伝送が可能といった特徴を持ちますが、 ファイバーケーブルや光コネクタの取り扱いには注意が必要です。 光ファイバーケーブルのイーサネットはISPやデータセンターで広く用いられ、 オフィスや家庭への引き込みにも使われています。
通信速度の向上
当初イーサネットは10Mbps (bit per second)でスタートしました。 そして10BASE5や10BASE2では1本の配線を共有しており、 同時に複数機器からは送信できません。 そのため規格のタイトルにもなっているCarrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)という手法がとられました。 これは送信する前に誰も送信していないことを確認し、 運悪く複数の機器が同時に送信して衝突を検出した場合は直ちに送信を中止してランダムな時間が経過した後に再送を試みる方法です。
この方法だと通信量が増大すると通信の衝突も増えて、 実効速度が低下することは容易に想像できます。 幸いなことに、10BASE-Tによって普及したハブが高機能化してスイッチングハブとなり、 複数の機器が同時に送受信できるようになったので、 通信の衝突は減っていきました。
そして1995年には、100Mbpsの速度をもつ100BASEシリーズが標準化されます。 最も普及したのは100BASE-TXですが、 10BASE-Tよりも高性能なUTPケーブルが必要になるため配線の交換が必要でした。 ただ、当時はまだLANもさほど普及しておらず、 比較的簡単に置き換え可能だったので順調に普及しました。
2025年時点で最も普及している1000BASE-Tは1999年に標準化されました。 100BASE-TXと同じ性能のUTPケーブルを使うため、 配線の変更は必要ありません。 通信速度は1Gbpsに達し、 条件次第ですがハードディスクを読み書きする速度と大差無かったりします。
2002年以降10Gbps以上、さらには1Tbpsに迫る規格も標準化されましたが、 1000BASE-T用よりも大幅に性能を向上させたUTPケーブルや光ファイバーケーブルが必要なこともあってか、 広範に普及したとは言いがたい状況です。 このため2016年に2.5GBASE-T、5GBASE-Tが標準化されています。 2.5GBASE-Tで使うのは1000BASE-Tよりも少しだけ性能の良いUTPケーブルで、 一般家庭向けとして普及が始まったところです。
https://standards.ieee.org/ieee/802.3/1057/





